最近の小学校や中学校では置き勉が禁止されている学校も多く、何かと不便なことが多いです。脱ゆとり教育で、教科書の重さが増えたのに対して、置き勉が禁止されているのは、かなり矛盾が生じています。置き勉の何がそんなにダメなのかは、実はあまり知られていません。
そもそもダメな理由はないはずです。
置き勉をしないことで、生徒のランドセルやリュックの重さはどんどん加速していき、まるで修行僧のように重い物を担いでいるのです。
ここでは、置き勉の意味や禁止される理由などを見ていこうと思います。
スポンサードリンク
そもそも置き勉をする意味とは?
置き勉はそもそも、下校する際に教科書やノートを持って帰らないで、学校に置いておく行為を指します。この文章だけでは、まるで生徒が怠けるためだけにやっているようですが、実際にはそうではありません。むしろ、バッグに入れる教科書の重みで、生徒の身体的負担が増えるのを阻止する役目もあります。つまり、置き勉をすることで、登下校のバッグの重さが軽減され、結果的に身体への負担が減るのです。
最近では、脱ゆとり教育に伴い、一日に使用する教科書の冊数が増えています。
そして厄介なことに、教科書の厚みもどんどん増大しており、余計に教科書の重量が増しているのです。なんと調査結果では、重いと10kgを超えたランドセルやリュックを背負っている子もいるようです。
特に中学生は10kgを超えることが当たり前となっています。部活の道具もあるので、教科書と一緒にリュックへ入れていたら、確かにそのくらいにはなってしまいそうです。
このように、生徒の身体的負担が増えるばかりなのに、置き勉を禁止する学校が増えているのはあまりにひどいことです。
しかし、学校側がこのような矛盾を作り出しているのには何か意味があるようです。
それにしても、意味があるないに関わらず置き弁をNGにする方がNGだと感じます。では、何故学校側は置き勉を禁止しているのでしょう?
置き勉がNGなのはどうして?
置き勉がNGな理由は実は不透明なことが多いのですが、学校側が置き勉をさせたくない理由は大きく分けて二つあります。
一つ目の理由は学校側からの一方的なメッセージで、「生徒は家に帰っても教科書で勉強しなければならない。そのため、教科書を持って帰る必要がある」というものです。その次は、失くし物を出したくないという学校側の意見です。教科書を持って帰りさえすれば、失くし物は出ないという考えでしょう。
そして三つめは、教科書にいたずら書きをされないようにです。しかし、これら三つには矛盾点が数多くあります。
家に帰ってから教科書で勉強した方が良いという言い分は分かります。ですが、教科書全てを持って帰ったからといって、全ての教科書を使って勉強することが一日で出来るのでしょうか?当然無理なことです。もし勉強や宿題をするにしても、その日に出された宿題の教科の教科書だけを持って帰れば良いのです。予習が必要なものも、必要に応じて持って帰ればそれだけで済むのです。それ以外の教科は、学校に全て置いて帰っても何も問題はありません。
臨機応変に教科書を持って帰れば良いのに、学校側は0か100のように考えていて、全てを持って帰るか帰らないかで考えすぎなのです。
そして、二つ目の理由にもかなり矛盾点を感じます。教科書を置いて行った方がむしろ失くし物がなくなりますし、第一教科書を盗む生徒などほぼいません。他の人の教科書を盗んでも何も得することがないためです。面白いことも一つもありません。三つ目のいたずら防止の観点も矛盾を感じます。そもそも生徒達は同じ時間に登下校するのですから、いたずらされる可能性はとことん低いです。
置き勉のデメリットは、このように全くないのにも関わらず、禁止されているのは、ただ単に昔から続いているという理由だけなのです。
置き勉禁止が始まったのは、いつか定まってはいませんが、今の30、40代くらいの方も置き勉は禁止でした。昔に置き勉が出来なかった人たちは、今の子が置き勉することも無意識にダメだと感じているのかもしれません。
スポンサードリンク
置き勉の最適な隠し場所はあるのか?
置き勉を禁止されていない学校であれば、ロッカーや机の引き出しに教科書を入れてそのまま帰宅します。しかし、禁止されている学校ではどこに置けばいいのでしょうか?そして、もし禁止が解かれた場合でも、どこに置くのが一番最適なのでしょうか?
禁止されている学校の子の中には、更衣室に置いていくという子もいました。部室に置いてしまうのも一つの手です。顧問にバレないようにするのが大変そうですが、気軽に取り出すことが出来ます。
中には、置き勉しても良い教科書などと一緒に置いておく方法もあり、地図帳や資料集などと一緒に置いている子も多いです。確かに、少しの量であれば先生にもバレることはないでしょう。とても賢いと思います。ジャージの下に置いておく方法もあります。隠せる幅が広がるので、かなり有効な手段です。
それにしても、置いても良い教科書もあるなんて、学校側の矛盾が大きく感じられます。紛れ込ませる系の置き勉方法は、その矛盾を逆手に取った方法だと言えますね。
また、習字や家庭科、音楽の道具も置き勉が可能なので、それらの大きな袋に教科書を入れている生徒もいます。
バレないようにする工夫が伝わってきて、感心すると同時につらいものも感じます。何故ここまでする必要があるのでしょうかね。早く置き勉が認められることを祈っています。
そして、置き勉が了承されたら、堂々とクラスのロッカーに入れてほしいです。了承をされているのならば、ロッカーが一番手っ取り早く教科書を出せますしね。
もし置き勉がバレた際はどう反省文を書いたら良いのか?
置き勉がバレると書かされるのが反省文です。ここまで来ると怒りよりも悲しみが湧いてきます。
書く方も本気で反省する気にはなれません。だって本当は置き勉は良いことなのですから。
それでもどうしても反省文を書かなければならない時は、自分を否定しない反省文を書きましょう。つまり、置き勉の行為だけを否定して、自分が悪かったなどの文は書かないのです。
例を挙げると、「私は毎日教科書を家まで持って帰るのが辛くて、置き勉をしてしまいました。今回反省分を書く機会をもらって、置き勉は悪いことだと再認識をしました。」など、このように自分は否定しないで、置き勉=悪いこととだけ書けばいいのです。
本当は置き勉は悪いことではないので、心苦しいですが、自分を守ることにだけ徹してください。生徒さんは何も悪くないのですから、自分が間違っていました反省しますなどは本来書かなくて良いのです。
このように、反省文を書かせる先生がいても、自分は悪くないのだと強く思ってください。置き勉は生徒の身体を助ける味方なのです。
まとめ
置き勉の矛盾点は尽きることを知りませんが、現状だとまだ置き勉が認められることはないのかもしれません、
生徒達は年頃ということもあり、あらゆる面で気を遣う子も多いでしょう。
しかし、身体がボロボロになったとしても置き勉が出来ません。生徒達をこんなに苦労をさせる必要はないのですが、昔からの風習ということで置き勉が認められていません。置いても良い教科書や道具があるのならば、全ての置き勉を許した方が賢明だと言えます。
時代の移り変わりに伴って、置き勉が認められる時代になれば良いなと感じています。
スポンサードリンク
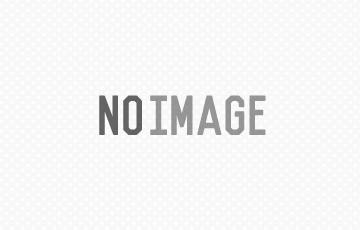
コメントを残す