お焚き上げって時々耳にする言葉ですが、いつどこで何のためにするのでしょうか?
お守りやお札、故人の遺品や人形など処分したいけどどうしたら良いのか?
困ることありますよね。お寺や神社で行われるお焚き上げについてご説明します。
スポンサードリンク
お焚き上げの歴史
お焚き上げはもともと密教の護摩行(ごまぎょう)が始まりといわれています。
火は神聖なものであり、悪いものが火の力で清められると考えられていました。
護摩行を通じて自分自身を見つめ直し行を修することで自分自身の煩悩を焼き払い心のゆがみを正していたのですね。
それを物の供養に応用したものがお焚き上げの始まりのです。お焚き上げの歴史は古く江戸時代には供養のために着物を焼いていたいという記述も残されています。
現在のお焚き上げ・利用のしかた
仏教特有の行為というわけではありません。人形供養などは神社でもお寺でも行われています。特別な信徒でなくても誰でも参加できます。
お焚き上げを利用したい方のためにいくつかの方法をご紹介していきます。
お焚き上げには基本的には出来るものと出来ないものの区別はありません。
しかし、場所によっては引き受けられるものを明確にしているところもあります。人形供養専門のところでもぬいぐるみは出来ないなどという場合もあるでしょう。
また、お寺や神社で授けられたお札・お守りなどはわざわざお焚き上げを依頼しなくてもそのお寺や神社に行けば集積場が設けられているところが多いです。
基本、神社のお守りは神社へお寺のお守りはお寺へお願いするのが良いでしょう。
お焚き上げが必要な品物の代表格としてはお守り・お札になりますが、お正月に購入する絵馬やお正月飾りなども一般的です。また、祈願のために購入した品物もお焚き上げしてもらうほうが良いでしょう。
スポンサードリンク
お焚き上げの費用・時期
お寺や神社にある集積場に置いておく場合は、お気持ち程度のお賽銭を供えましょう。
ただ、お正月を過ぎると閉じられてしまうことが多いのでその場合は寺社仏閣に聞いてみましょう。
お寺や神社によって違いますが一般的にはお焚き上げをしてくれる時期は正月三が日が多いです。
長いところでは10日位までです。そのあとは、一月中旬(1月15日前後の土日)にかけてどんと焼きが行われるところもあるでしょう。
神棚の処分はお焚き上げ?
神棚の処分の場合はお焚き上げでは対応できずお寺や神社の神棚処分という形になります。
神棚処分は、お寺や神社の祈祷受付所に行き受付してもらいましょう。
神棚処分はお賽銭ではなくご祈祷料をお納めします。費用相場は3000円から10000円程度です。神棚の大きさや祈祷に立ち会うかによって値段は変わってきます。
神棚処分に対応しているかは神社やお寺によって異なりますので事前に電話などで確認しておきましょう。その際に費用についても確認しておきましょう。
場合によってはお気持ち程度のお礼をお納めする値段が決まっていない場合もあるそうです。その場合でも最低でも数千円、一般的には3000円から5000円ほどお包みするのが良いでしょう。
まとめ
・お焚き上げはもともと密教の護摩行(ごまぎょう)が始まりといわれていわれており、悪いものが火の力で清められるということを物に応用したものがお焚き上げの始まりといわれています。
・お焚き上げには基本的には出来るものと出来ないものの区別はありません。
・お守りやお札は授かったお寺へ神社の集積場へ持っていきましょう。その際はお気持ち程度のお賽銭を供えましょう
・一般的にはお焚き上げをしてくれる時期は正月三が日が多いです。長いところでは10日位までです。そのあとは、一月中旬(1月15日前後の土日)に持っていきましょう。
・神棚の処分の場合はお焚き上げでは対応できずお寺や神社の神棚処分という形になります。
費用相場は一般的に3000円から10000円程度ですが様々ですので、神棚処分に対応しているかを含めて事前に電話などで確認しておくと良いでしょう。
お守りやお札はお正月に神社やお寺に初詣でお参りした際に購入することが多いと思います。
一年間自分や家族をお守りしてくれた大切なお守りやお札は感謝の意味を込めてお焚き上げしてもらい、その神社やお寺にまた新たにお授けしてもらうと良いですね!
これで気持ちよく日々を過ごせそうです。お焚き上げという風習は日本独自の今も昔も変わらない日本の心といえるでしょう。
遺品には故人の魂が宿るといわれています。遺品整理においては遺品供養はとても大切なことといえるでしょう。
日本ではたとえ物であっても神仏化したものやそうでないものでも丁寧に扱っていますね。
これからもずっとずっと大切にして守っていきたい風習ですね。
スポンサードリンク
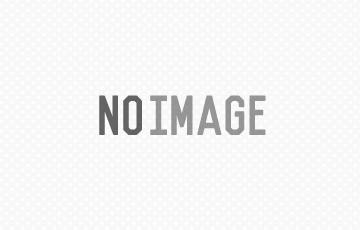

コメントを残す